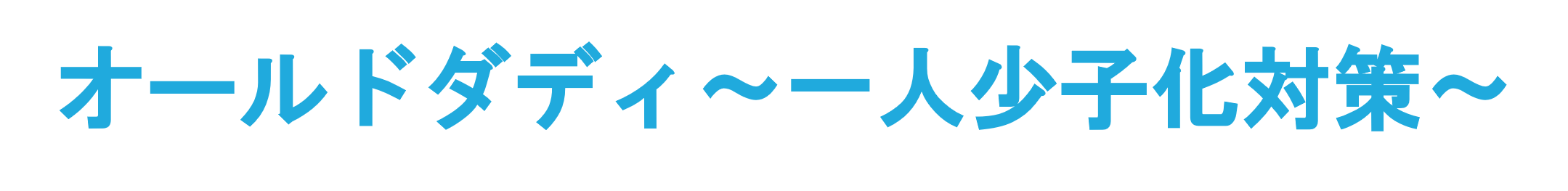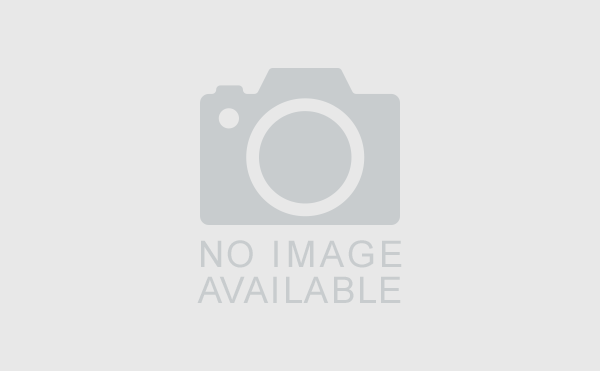何故日本では子供を持つのに結婚しなくてはいけないのか?
少子化は世界的に進行している現象ですが、その背景には国ごとの社会構造や文化的価値観の違いが深く関係しています。特に出生率(合計特殊出生率)と婚外子比率(非嫡出子の割合)を比較することで、出産や家族形成に対する考え方の違いを浮き彫りにすることができます。
この記事では、アメリカ、フランス、イギリス、日本、中国、韓国の6か国を対象に、出生率と婚外子比率を比較し、それらの数値の背後にある社会的・文化的要因について考察します。特に、東アジア諸国(日本・韓国・中国)の特徴的な家族観や価値観についても掘り下げて論じます。
各国の出生率と婚外子比率(2023年推定値)
| 国名 | 合計特殊出生率 | 婚外子比率(%) |
|---|---|---|
| アメリカ | 1.67 | 約40% |
| フランス | 1.79 | 約62% |
| イギリス | 1.55 | 約50% |
| 日本 | 1.26 | 約2.5% |
| 中国 | 1.09 | 約6% |
| 韓国 | 0.72 | 約2.5% |
出生率が最も高いのはフランス(1.79)、次いでアメリカ(1.67)です。反対に、韓国(0.72)はOECD諸国の中で最も低く、日本(1.26)と中国(1.09)も低水準にあります。婚外子比率に注目すると、フランス(約62%)、イギリス(約50%)、アメリカ(約40%)が高く、欧米諸国では結婚を前提としない出産が一般化していることがわかります。一方で、日本と韓国は2.5%程度、中国も約6%と、アジア諸国では婚外子が非常に少ない傾向があります。
欧米諸国の特徴:自由な家族観と多様性(ダイバーシティ)
フランスやイギリス、アメリカでは、1970年代以降に家族観の多様化が進みました。事実婚や同棲、シングルマザーによる出産などが一般的となり、婚外子が社会的に受容されています。特にフランスでは、PACS(市民連帯契約)という事実婚の制度が広く普及しており、法的保護もあります。
これらの国では、出産に結婚が必須条件とは見なされず、個人のライフスタイルや価値観が優先される傾向にあります。また、保育制度や育児支援が整っており、家庭の形態にかかわらず子どもを育てやすい環境が整備されています。そのため、婚外子の増加がむしろ出生率の維持に貢献していると考えられます。
東アジア諸国の特徴:伝統的家族観と婚外子への偏見
対照的に、日本・韓国・中国の東アジア諸国では、婚外子比率が非常に低く、それが出生率の低下に直結している可能性があります。これらの国では、依然として「結婚してから出産するのが当然」という価値観が社会の中で強く存在しています。その背景には、以下のような文化的・制度的要因が挙げられます。
儒教的価値観と家族のあり方
東アジアでは、儒教の影響を色濃く受けた家族観が長年にわたって形成されてきました。儒教では、家族は社会秩序の基盤であり、子どもは正規の結婚関係の中で生まれるべき存在とされています。家制度や家父長制の名残が今も根強く、家系の存続や親の名誉を重んじる文化が婚外子に対する否定的な見方につながっています。
また、婚外子は「恥」として見なされることもあり、本人だけでなく親族全体が社会的非難の対象となることがあります。特に地方や高齢層においては、この傾向が顕著です。
法制度の未整備
文化的偏見に加えて、未婚の親や婚外子に対する制度的支援が不十分であることも問題です。
日本では、長らく戸籍上で非嫡出子と記載され、法的にも相続などで差別が存在していました。現在ではこの表記は撤廃されたものの、制度的な壁はなお残っています。また、保育や育児支援の多くは夫婦を前提に設計されており、未婚の親に対する支援は限定的です。
韓国も同様に、未婚の母親に対するスティグマが強く、制度的なサポートも少ないため、事実上シングルでの出産は大きなリスクを伴います。
中国では、かつての一人っ子政策や婚外出産への罰則的措置の影響により、婚外子の存在そのものが制限されていた歴史があります。現在では制度が緩和されつつありますが、都市と農村での格差や、社会的な偏見は依然として存在します。
出産=結婚という考え方
これらの国々では、出産が結婚制度と強く結びついているため、若者の未婚化・晩婚化がそのまま出生率の低下につながっています。たとえば日本では、経済的不安定さや雇用の非正規化が進む中で、結婚そのものを先延ばしにする傾向が強まり、その結果として出産も減少しています。
一方で、欧米のように「結婚しなくても子どもを持てる社会」にはなっておらず、社会的・制度的なサポートも不十分なため、個人が柔軟に家族を形成することが難しい状況です。
日本では「将来結婚と子供について」というアンケートに、結婚はしなくても将来的に子供が欲しいと答えた人は9.4%でした。
「将来、子どもがほしくない」Z世代の約5割
BIGLOBEが「子育てに関するZ世代の意識調査」を実施
私の考えですが、子供は欲しいが結婚はしたくないという方はおそらくもっと多く、今後も増えると思います。
現代では必ずしも夫婦で力を合わせなくても1人でも生きていける社会になっており、男女ともに一緒に暮らす必要もなくなってきたと考えている人は増えていると思います。
また、厚生労働省が実施した「結婚と出産に関する全国調査」では、「結婚せずに子どもを持ってよい」という考えを支持する人は3割台であることが報告されています。
第 14 回出生動向基本調査
結婚と出産に関する全国調査
独身者調査の結果概要
現在ではまだ日本はこの考えを指示できる人は少ないと思います。
最近著名人で選択的シングルマザーとなった方がSNSで発表した際には、無責任だという声も多くありました。
もちろん、そういった意見を否定するつもりはありませんが、私は子供の幸せに父親が必要不可欠だとも思いません。
今後時代が進むにつれ、世代が移り変わり女性一人でも十分に生計が成り立つ人が多くなった時に、「結婚せずに子どもを持ってよい」という考えを支持する人の割合はさらに増えてくると思います。
少子化対策としての価値観の転換
少子化を食い止めるためには、経済的支援や保育サービスの充実に加えて、社会全体の価値観の見直しが必要です。すなわち、結婚という形式に依存せずとも出産・子育てができる社会の実現が求められます。
そのためには、以下のような施策が考えられます。
- 事実婚や未婚の親に対する法的保護の拡充
- 婚外子やシングルペアレントへの差別撤廃と社会的理解の促進
- 出産・育児支援制度の家族形態に依存しない再設計
- 学校教育やメディアを通じた家族観の多様性への啓発
東アジアにおける強固な家族観は、長い歴史の中で築かれてきたものではありますが、時代の変化に対応する柔軟性が求められています。個人の選択を尊重し、多様な家族の形が自然に受け入れられる社会へと転換することが、出生率の回復につながる可能性があります。
まとめ
出生率と婚外子比率の国際比較は、単なる数値の違いだけではなく、各国の文化、価値観、社会制度のあり方を反映しています。特に東アジア諸国では、伝統的な家族観や制度上の制約が、未婚出産のハードルを高くし、少子化を加速させる要因となっています。
今後は、個人の生き方や家族形成に対する柔軟な価値観を社会が共有し、どのような形であっても「子どもを持ちたい」と思える環境を整えることが求められます。そのためには、制度の整備だけでなく、教育や意識の面からの改革も必要不可欠です。
もちろん、無責任に子供を作ればいいかというとそうではありません。
ただ、少子化という課題に立ち向かうには、社会全体が変わる覚悟と、未来世代の多様なライフスタイルを受け入れる寛容さが求められているのです。
そして、これを読んでいる方には是非、選択的シングルマザーでも子供が欲しいという希望を捨てずに叶えていただきたいと思います。
もし私に依頼していただければ援助をしっかりとしていきたいと思います。